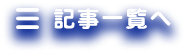【2025年最新】不動産取引における電子契約の流れを解説!導入デメリットから導入事例もご紹介!
タグ:

目次
▼媒介契約・売買契約に対応!
いえらぶの電子契約サービス情報を見てみる
不動産取引における電子契約も、2021年9月1日にデジタル改革関連法が施行されたことをきっかけに本格化しました。これまで書面化の義務があった手続きも、法改正に伴い電子化することができます。
今回は、不動産契約の電子化を導入する際に、注意しなければならないことを解説します。
電子契約とは
電子契約は電子ファイル上に、電子署名することで契約証明する方法のことです。
電子契約は新型コロナの影響で世間のニーズが高まり、注目されています。実際に弊社独自で行った調査によると、Z世代の8割以上が部屋を借りる際、電子契約を希望しているという結果が得られています。

Z世代の8割以上が部屋を借りる際、電子契約を希望!不動産会社の導入状況とのギャップも(いえらぶ調べ)|いえらぶニュース|不動産業務支援システムのいえらぶCLOUD
書面契約と電子契約の違い
従来の書面契約では、紙の契約書に印鑑や印章で押印をおこなっていました。
しかし、電子契約では紙の代わりに電子データで契約書を作成し、押印の代わりに電子署名を用います。
電子署名には本人であることを証明する電子証明書、非改ざん性を担保するタイムスタンプが使われるため、有効性のある手段です。
不動産取引における電子契約の広がり
現在、電子契約は多くの業界で取り入れられていますが、不動産業界においては長らく法律によって電子化が困難な状況でした。
しかし、2021年に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、これにともなって宅建建物取引業法にも変更が加えられました。
主に不動産業界にインパクトを与えた内容は以下の2つです。
1.重要事項説明書への宅地建物取引士のハンコが不要になり、電子署名で対応可能になった。
2.重要事項説明書などで定められていた書面での交付義務がなくなった。
これらにより、不動産業界でも取引書類の電子化が進められるようになりました。
▼媒介契約・売買契約に対応!
いえらぶの電子契約サービス情報を見てみる
不動産取引における電子契約の締結完了までの流れ
電子契約に移行した後も、契約の流れに大きな変化はありません。ただし、紙の書類を利用する場合とは異なる作業が生じます。
ここでは賃貸借契約と売買契約を想定して、ステップごとに主な作業内容を紹介します。
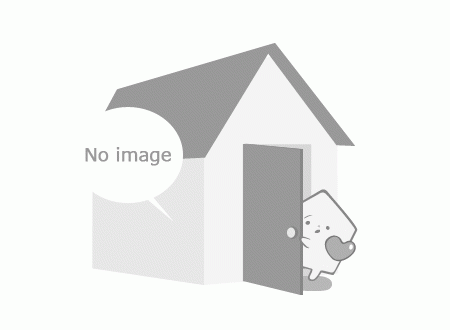
1.入居申込み/購入申込み
借りたい・買いたい物件が決まったら、入居申込み/購入申込みをします。
賃貸借であれば、借主が貸主や家賃保証会社から審査を受けます。
売買であれば、買主がこの時点で金融機関に住宅ローンの事前審査も申し込むことになります。
2.重要事項説明(IT重説)
審査が通ったら、借主・買主に対して重要事項説明を行います。
ここでは、買主や借主に対してオンラインで重要事項説明を行う「IT重説」を想定して説明します。
従来の方法と同じく、宅地建物取引士が重要事項説明を行います。Web会議ツールなどを使用して行うのが一般的ですが、買主や借主の希望によって対面(オフライン)で行う場合もあります。
IT重説を行うにあたって注意すべきことは、下記のとおりです。
・IT重説の承諾の記録を残す
・承諾後でも書面への変更ができることを伝える
・送付した重要思考説明書などに改変がないか確認する
・宅地建物取引士証はカメラにしっかりと映す
IT重説は相互の承諾のうえで行っていることがわかる必要があります。承諾を証明できる記録を残しましょう。重要事項の説明時は互いに内容を確認し合い、買主や借主が内容を改変していないことも確認します。
間違いなく有資格者がIT重説を行っていると証明するために、宅地建物取引士証はしっかりとカメラに映しましょう。
3.契約書面の電子交付
書類の真正を証明するため、重要事項説明後には35条書面(重要事項説明書)・37条書面などの契約書面を電子交付します。紙の書類と同じく、電子契約においても買主や借主の記名押印が必要です。
重要事項説明書を電子交付するときは、なりすましに注意しましょう。目の前で記名押印する様子が確認できる対面での契約と異なり、オンラインは本人以外がなりすましても気付きにくいリスクがあります。
また、互いに重要事項説明書の文案を照らし合わせて、改変がないことも確認しましょう。オンラインによるやり取りであっても、必ず契約当事者同士が確認することが大切です。
4.締結完了・入居/引渡し
署名・押印に問題がなければ、契約締結完了です。
賃貸借契約の場合は、実際に入居できるのは事前に借主・貸主間で取り決めた入居日です。売買契約であれば、締結完了したうえで手付金の入金を済ませてから物件の引き渡しとなります。
紙だと押印位置を間違えたり署名の抜け漏れが発生したりといったリスクがありますが、電子契約であればそういった人的ミスは起こりません。
システムの案内に従って署名・押印作業をすれば確実に契約締結が完了するのも、電子契約の強みです。
▼電子契約の準備の流れもチェック!
「電子契約に関する法律マニュアル」をダウンロード
不動産取引で電子契約が可能な主な書類
不動産取引において電子契約可能な書類は、情報登録や契約締結に関連するものがほとんどです。2024年1月時点で電子契約可能な主な書類は以下のとおりです。
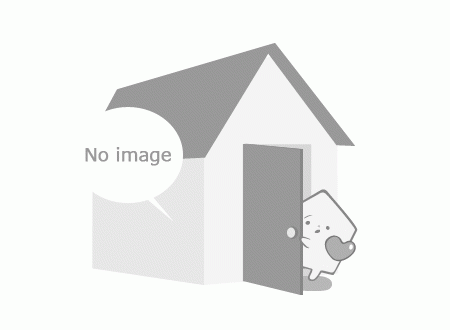
媒介契約締結時書面
媒介契約書は、不動産会社に仲介を依頼する際に締結する文書です。不動産の売主・買主と不動産会社の間で交わす「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類が該当します。
指定流通機構への登録を証明する書面
売却に出されている物件の情報は、指定流通機構(レインズ)で複数社に共有されます。レインズに物件を登録すると売主に証明書が発行される仕組みになっていましたが、この書類も電子化の対象となりました。
重要事項説明書
不動産の売買や賃貸借契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が物件に関する重要事項を説明するよう法律で義務付けられています。説明時に買主や借主へ交付する物件の重要事項説明書も電子化が可能になりました。
契約締結時書面
不動産の売主・買主に対して発行する売買契約書のことです。37条書面とも呼ばれ、不動産売買契約書も同じ書類を指します。
▼媒介契約・売買契約に対応!
いえらぶの電子契約サービス情報を見てみる
不動産取引で電子契約を実施するときに注意する法律
実際の不動産取引で電子契約をする際に注意すべき法律は、「電子署名法」と「電子帳簿保存法」です。
以下では、それぞれの法律の内容と注意点を解説します。
電子署名法
書面に押印と記名をして行っていた契約を電子化すると、契約を法的に証明できるのかという懸念があるかもしれません。
法的に有効な「電子署名」について定めている「電子署名法」という法律があります。
電子署名法では、第2条で「本人が行ったこと」と「改変されていないこと」が確認できるものを「電子署名」として定義しています。また、第3条では「本人しかできない電子署名がされている」ことを確認できれば、電子署名で締結した契約が法的に有効であると定められています。
電子署名法を満たした電子署名を行えるサービスを提供する事業者は、国が認定しています。
不動産会社が電子契約のシステムを導入するときは、電子署名法を満たしていて、法的に有効な電子契約ができることを国から認められている企業のシステムを入れることが最も安全です。
いえらぶGROUPが提供する電子契約システム「いえらぶサイン」は、国から認可を受けている弁護士ドットコム株式会社の「クラウドサイン」、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「電子印鑑GMOサイン」と連携した不動産業務特化型の電子契約サービスですので、安心してご利用いただけます。
参照:電子署名法に基づく特定認証業務の認定について | 法務省
参照:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索
電子帳簿保存法
電子契約で締結した契約書のデータは、電子帳簿保存法を満たした形式で電子的に保管することが義務付けられています。
以前は電子契約で締結した契約書を印刷して書面で保管しておくことが認められていましたが、2022年1月以降に行う電子契約については、電子ファイルでの保存が義務化されました。
また、2023年12月末までは宥恕期間が設けられていましたが、2024年1月からは電子帳簿保存法への対応が求められているので注意が必要です。
電子帳簿保存法で特に確認が必要なのは、電子ファイルの契約書が改ざんされていないことを証明できることと、必要な時に速やかに画面・書面に出力できるように保管しておくことです。
タイムスタンプの付与や保存する場所として必要な環境が細かく定められているので、ファイルの保管を行うシステムで電子帳簿保存法に沿って保管できるかを確認してください。
参照:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 | e-Gov法令検索
不動産電子契約に関する法律についてはこちらの記事で網羅的にまとめています。ぜひ併せてご確認ください。
2023年最新版不動産電子契約に関する法律まとめ不動産取引に電子契約を導入する6つのメリット
不動産会社に電子契約を導入するメリットを紹介します。
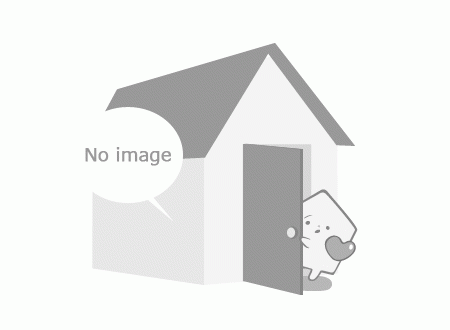
①業務効率化
電子契約は時間・場所に縛られず契約可能で、取引先までの移動・郵送の時間・経費の節約ができます。
郵送での契約には、時間がかかっていました。不動産会社から書類を郵送し、契約者が受け取ってから記入して返送するという流れになるため、完了までにどんなに短くても数日から1週間程かかります。
オンライン化することで書類の受渡しに時間がかからなくなり、最短数時間で契約業務が完了できる場合もあります。
さらに、書類の受渡しにかかる時間の短縮だけでなく、製本や郵送の作業など契約業務の手間も減らせます。対面で契約業務を行っていた場合は、日程調整やお客様の対応などの業務も効率化できます。
電子契約の導入に加えて不動産業務システムを利用することで、さらなる業務効率化も可能です。
②コストカット
書面契約でかかっていた印紙代・郵送代だけでなく、それら業務にかかる人件費まで節約可能です。
書面で契約を進める場合、書類の製本や郵送に費用がかかります。返送されてきた書類に不備があるなど、再郵送のために追加で費用がかかることもあります。
オンライン化することで、印刷費用、製本費用、封筒代、郵送費用などの郵送にかかる様々な費用が削減できます。
また、電子契約の場合は印紙税が発生しません。
売買契約であれば印紙税は数万円〜数十万円かかるため、電子契約を導入するメリットは大きいと言えます。
③保管場所が不要
電子契約では契約書面がオンライン保存され、物理的な保管場所が不要になり、いつでも内容を確認できます。
保管に必要な場所の確保にかかっている費用が削減されるだけでなく、システムを利用してデータの保管方法を工夫すれば、災害時などに大切な書類のデータが消えてしまうリスクにも対応できます。
④働き方改革に大きく貢献
電子契約の導入は、コロナウイルスの影響による「在宅ワーク」や「テレワーク」といった新しいワークスタイルの導入にも大きく貢献します。
電子契約により契約締結までスピーディーに完了できるようになれば、契約者やオーナー様など、不動産会社のお客様の満足度も向上できます。
⑤書面契約より少ない工程でスムーズに契約完結
従来の書面契約では、紙の契約書の作成や宅地建物取引士の記名押印が必要でした。さらに、契約書に規定の収入印紙を貼付し、印紙税を収める必要もありました。
電子契約では、紙の契約書の印刷、製本、宅地建物取引士の記名押印といった業務が一切不要になります。
印紙代のコストカットや、契約に際してこれまでおこなっていた業務上の複雑なやり取りを減らすことが可能です。
⑥消費者のニーズの高まり
コロナ禍がきっかけとなり外出自粛やテレワークが広がり、内見や重要時事項説明を自宅で済ませたい、さらには契約もオンラインで結びたいというニーズが高まっています。
手続きをオンライン化することで、そのような消費者のニーズに応えることができ、顧客獲得につながります。
電子契約システムの選び方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
不動産取引に電子契約を導入するデメリットと注意点
電子契約導入にともない業務効率化が向上する一方で、デメリットが生じることもあります。自社に電子契約を導入するときは、デメリットも考慮したうえで慎重にシステムを選ぶことが重要です。
電子契約導入で生じやすいデメリットや注意点は、次の5つです。
契約関係者の事前承諾を得る必要がある
重要事項説明書の交付や売買契約、媒介契約など、不動産業界における契約の多くは「事前承諾を得る」ことが電子契約の要件に含まれます。
契約相手が書面による契約締結を希望している場合は電子契約ではなく、紙に印刷した契約書で対応する必要があります。
電子契約を導入するときは、書面を希望する相手にもスムーズに対応できるように、書面による契約も残しておくことが大切です。
また賃貸借契約を締結する際には、家主からも電子契約の承諾を得る必要が出てくるでしょう。
家主からの理解を得ることに課題を感じる不動産会社は多く、会社によって様々な工夫が見受けられます。
契約関係者からの理解を得ることに課題を感じている方は、後述する「不動産取引における電子契約の運用事例」や「電子契約運用事例」に載っている他社の工夫を参考にしてみてください。
▼電子契約、契約関係者にどう協力してもらう?
不動産会社向けに徹底解説!電子契約運用事例
「電子署名をおこなう当事者は誰か」に注意が必要
契約にかかわる当事者が誰かという点には、注意が必要です。
一般的な不動産取引では、「売主または貸主」、「買主または借主」のほか、重要事項説明などをおこなう「宅地建物取引士」の三者が契約に関与します。
また、電子署名をおこなうとはいえ、非対面の契約にはなりすましのリスクが伴います。
電子契約サービスなどを用いて、契約当事者が本人かどうかを確認できる仕組みを導入することで対策しましょう。
さらに、取引額の大きい売買契約や媒介契約であれば「犯罪収益移転防止法」の対応も必要です。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリング(資金洗浄)や犯罪組織への資金提供を防ぐために施行された法律です。
売買・媒介契約などの取引をする場合、個人・法人の本人特定事項(氏名や生年月日など)、取引の目的、職業・事業内容といった情報を確認する義務が課されています。
データ漏えいや改ざんのリスクがある
重要な契約書類は取り扱いに注意しなくてはなりません。たとえば紙の書類の場合は鍵をかけられるチェストに保管するといった盗難対策が必要です。デジタルツールを利用する電子契約の場合もデータ漏えいや改ざんのリスクがあります。
データ漏えいや改ざんが生じる原因は、さまざまです。データが入ったUSBの紛失をはじめ、SNS画像にパスワードが移り込んだり、サイバー攻撃を受けたりするなど、思わぬ経緯でトラブルが生じることがあります。
従業員に対するセキュリティ教育はもちろん、システム面での対策が欠かせません。ウイルスやサイバー攻撃に備えたセキュリティサービスを導入する、こまめにデータのバックアップを実施するなどして、データ漏えいや改ざんリスクを軽減しましょう。
業務フローの再構築が必要な場合がある
電子契約の導入により、契約業務だけを電子化することも可能です。一度にすべての業務を電子化する必要はありません。無理のない範囲から導入することをおすすめします。
とはいえ不動産会社によって業務フローが異なるため、導入する過程で業務フローの再構築が必要となる場合もあります。既存の業務フローを再構築する際は、新しいマニュアルの作成も必要になります。この場合は、準備や適応に工数がかかることを想定したスケジュールを立てることが大切です。
▼媒介契約・売買契約に対応!
いえらぶの電子契約サービス情報を見てみる
不動産取引における電子契約の運用事例
更新契約を電子化(株式会社日本財託管理サービス)

全体の7割の入居者に対して、電子契約での更新契約を行っている日本財託管理サービス様。以下、日本財託管理サービス様のコメントです。
「紙の契約から電子契約に切り替えたことで、事務作業が減りました。以前は書面が戻ってくる度に捺印し直して返送する手間がありましたが、今はその手間がなくなっています。
現在、契約更新時に電子契約を案内した方の約7割が電子契約を使ってくれています。例えば2023年9月だと、700件中500件ほどを電子契約で行いました。月500件分の事務作業が軽減されているので、効果はかなり感じています。」
日本財託管理サービス様の事例詳細はこちらをご覧ください。
株式会社日本財託管理サービス様|いえらぶCLOUDの評判・口コミ【導入事例】
賃貸借契約を電子化(株式会社ヘヤミセ)
賃貸借契約・更新契約の電子化に成功し、社員から「電子契約じゃないと嫌だ」という声が上がるまでになったヘヤミセ様。以下、ヘヤミセ様のコメントです。
「今まではIT重説をするときに契約書を印刷して郵送していました。郵送には時間がかかるので、重説する日から逆算して早めに契約書を作る必要があったんですね。
電子契約にしてからは郵送の時間がかからなくなったので、その問題が解決しました。以前は重説の5日前までに契約書を作成する必要がありましたが、今は前日・前々日くらいに契約書を送れば、余裕をもって重説を進められるようになっています。」
ヘヤミセ様の事例詳細はこちらをご覧ください。
株式会社ヘヤミセ様|いえらぶCLOUDの評判・口コミ【導入事例】
▼電子契約、契約関係者にどう協力してもらう?
不動産会社向けに徹底解説!電子契約運用事例
管理委託契約を電子化(株式会社T様)
30件以上の管理委託契約を、電子契約を使って締結しています。
オーナー様を相手に二者間で締結するのが基本なので、電子化して業務が複雑になることは特になく、スムーズに締結できています。
売買契約を電子化(株式会社F様)
買主様が海外に在住されていることもあり、売買契約を締結する際にIT重説や電子契約を活用しています。
送信する書類には、IT重説や電子契約の同意書、買主様の情報がまとまった「顧客カード」というものも含んでいます。それぞれ宅建業法や犯収法を遵守するための書類です。
電子契約システムならいえらぶサイン
「いえらぶサイン」は、弁護士ドットコム株式会社の「クラウドサイン」、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「電子印鑑GMOサイン」と連携をしているため、電子署名と認定タイムスタンプに対応した電子契約を行うことができます。
不動産専門の電子契約システムですので、不動産会社様の業務フローに沿った設計や、基幹システム「いえらぶCLOUD」とのデータ連携など、使い勝手にもこだわっています。
いえらぶサインの効果
いえらぶサインの効果に関して、弊社独自で調査を行いました。
賃貸借契約締結にかかる平均期間が、紙では「4日以上」の回答が84%を占めていたのに対し、電子では「3日以内」の回答が77.8%を占め、いえらぶサインを導入することで契約締結期間が大幅に短縮できることが分かりました。
さらに、いえらぶサインを利用した更新契約の51.8%が翌日までに契約完了できているという結果も出ています。
いえらぶサインの3つのポイント
①契約の締結がどこでも可能に
オンライン上で契約のやり取りが完結するため、時間・場所に縛られることがなくなります。
また、物理的な契約書類の保管場所が不要です。
②様々な契約フローに対応できる
各社異なる契約フローにも、いえらぶサインはカスタマイズ機能により対応しています。
③物確から契約まで一気通貫でサポート
「いえらぶCLOUD」は不動産関連業務を網羅する業務効率化ツールなので、契約に至るまでの業務もサポートします。
連携して使うと便利な機能
不動産業務効率化ツール「いえらぶCLOUD」を導入していただければ、物確から契約まですべての不動産業務を、流れるように一元管理していただけます。
「いえらぶCLOUD」は不動産仲介会社様から不動産管理会社様まで、幅広い業態でお使いいただけます。
電子契約への切り替えの際には是非「いえらぶサイン」の導入をご検討ください!
まとめ
不動産契約の電子化が全面解禁されたことで、業務効率化やコストカットが図れるようになりました。一方で、セキュリティ上のリスクや業務フローの複雑化といった問題が生じるおそれもあります。
電子契約に対応するには、新たにセキュリティ対策を講じたり業務フローを確立したりすることが必要です。電子契約システムを導入する際は、ぜひ「いえらぶサイン」をご活用ください。
▼媒介契約・売買契約に対応!
いえらぶの電子契約サービス情報を見てみる