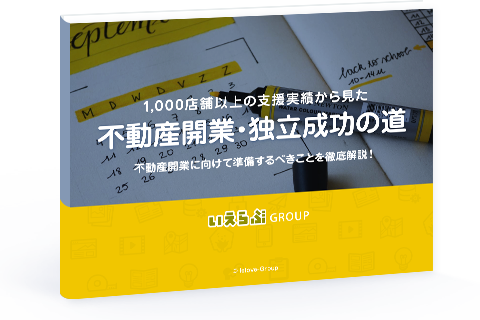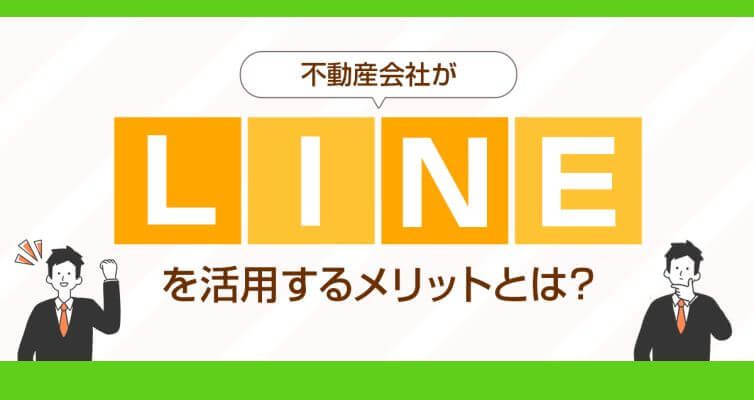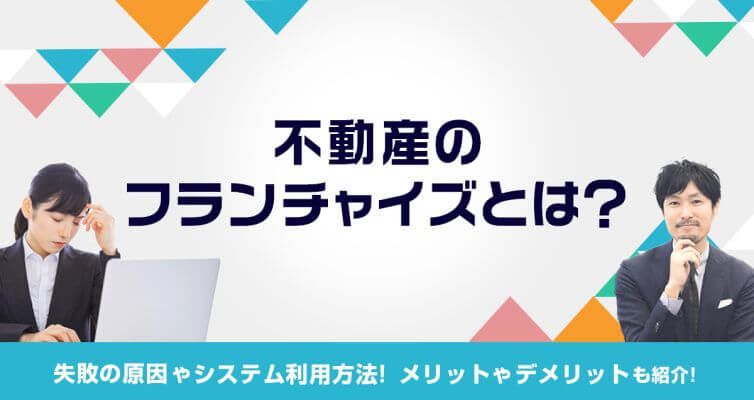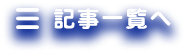不動産開業の資金を融資!融資の条件や創業計画書のポイントを解説
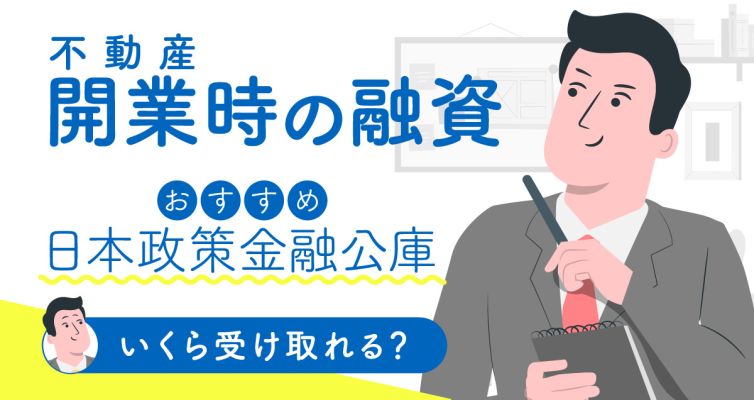
目次
▼不動産開業、どう成功させた?開業した方々の事例集公開中!
事例集資料をメールで受け取る
不動産業を始めるには、まず開業資金の融資を確保する必要があります。しかし、融資は必ずしも受けられるものではなく、審査を通過するための事前準備が欠かせません。
では、融資はいくら必要で、融資を受けるために満たすべき条件にはどのようなものがあるのでしょうか。この記事では、不動産業を始めるために知っておきたい「開業資金の融資」についての情報をご紹介します。

不動産の開業に必要な資金は400万円
不動産業を開業する際に必要になる資金は約400万円だといわれています。これは、不動産仲介業を開業する際に必要になる最低限の目安です。
不動産業の開業にかかる費用の内訳(目安)は以下のとおりです。
| 法人設立費用 | 約24万円 |
|---|---|
| 不動産協会加盟の入会金 | 130万円~180万円 |
| 宅建業者免許申請料 | 3万3,000円 |
| 事務所設置の初期費用 | ~20万円 |
| その他諸経費 | ~200万円 |
上記費用はあくまで目安であり、当面の生活費として数ヶ月分程度の費用を準備しておくなど、別途必要になる資金もあるでしょう。
不動産業開業には、営業保証金として1,000万円を法務局へ支払いする義務がありますが、上記の内訳には含まれておりません。
営業保証金は、全日本不動産協会などの「保証協会」に加入して分担金を支払えば、支払い義務を放棄できるため、必須の費用ではないからです。また、事業用として使用する車両や事務所として使用できる物件を所有していれば、初期費用を安く抑えることができます。
開業資金に限らず、事業拡大資金や、会社の運転資金など、融資はさまざまな場面で利用する機会が生じます。開業資金で融資を受ける際は、将来的に別の用途で融資を受ける可能性も考慮して、無理のない範囲に抑えることが大切です。
不動産業の開業資金に関する詳細は、下記のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
不動産仲介業の独立開業に必要な資金はいくら?開業の手順も解説
▼不動産開業、どう成功させた?開業した方々の事例集公開中!
事例集資料をメールで受け取る

不動産業の開業資金の融資を受けられる機関
不動産業を開業するにあたり、開業資金確保のために金融機関からの融資を考える人は多いのではないでしょうか。
では、不動産業の場合には、どのような金融機関から融資を受けることができるのでしょうか。ここからは、不動産業の開業資金の融資を受けられる機関やそれぞれの特徴について紹介します。
日本政策金融公庫が一般的
不動産業の開業なら、「日本政策金融公庫」からの融資が一般的です。
日本政策金融公庫は株式会社ですが、国が株式を100%保有しています。日本公庫が株式会社の形態をとっているのは、株式会社のガバナンスの仕組みを活用して、透明性の高い効率的な事業運営を行うためです。
分かりやすくいえば、政府公認の金融機関だといえるでしょう。
日本政策金融公庫は政府公認の金融機関として3つの役割があります。
セーフティネット機能の発揮 |
自然災害や経済環境の変化などによる、セーフティネット需要に機動的に対処。 |
|---|---|
日本経済成長・発展への貢献 |
新たな事業の創出、事業の再生、海外展開及び農林水産業の新たな展開などのニーズに適切に対応。 |
地域活性化への貢献 |
民間金融機関と連携し、地域プロジェクトに参画するなどの地域活性化に貢献。 |
主な融資先としては「民間金融機関から融資を受けづらい事業者」だといえるでしょう。
以下に具体的にあげてみます。
・中小企業
・個人事業者
・これから創業、あるいは創業して間もない事業者
金利負担の軽さが最大の強みで、融資制度の大半が利率1%台か2%台です。比較的融資を受けやすいと言われる銀行のビジネスローンでも6~7%程度のため、金利負担の軽さが大きな魅力でることが分かります。
また、低金利であるのにも関わらず、金利が変動しない融資制度も多いです。
また、日本政策金融公庫は、無担保・無保証でも融資が受けられる融資制度もあります。
融資額を上げたい場合は自治体からの融資も検討する
自治体には、信用保証協会や金融機関と協調して中小企業・創業者向けに融資を行う「制度融資」が存在します。自治体によっては、金利の優遇、信用保証料の割引・免除など、より融資を受けやすくしているところもあります。
制度融資のメリットは、日本政策金融公庫からの融資と併用できることです。さらに、日本政策金融公庫よりも、金利が1%程度低いことがあげられます。融資額を上げたい場合は、併用前提で自治体の制度融資も検討の余地があります。
利用時の注意点として、申し込みから融資実行まで日数がかかることがあげられます。申し込みから2〜3ヶ月はかかるので、日数を逆算して計画的に申請の手続きを進めなければなりません。また、居住年数制限もあるため、地元へのUターンなど開業にともない引越しを計画している場合は事前に確認しておくことが大切です。
銀行からの融資は難しい
不動産業の開業資金を銀行から融資を受けるのは、難しい傾向にあります。銀行の融資は、企業の経営実績やこれまでの銀行との付き合いなどが考慮されるためです。
実績のない新規企業に対して、銀行が融資を行うケースは極めて稀です。信販会社やリース会社、消費者会社などのいわゆるノンバンクも利用することはできます。ノンバンクとは預金業務を行わず、主に融資業務を取り扱う金融機関のことです。
個人向け融資を行っている消費者金融などの中にも、ビジネスローンを取り扱っているところがあります。担保や連帯保証人なしでも借りられる場合がある点がノンバンクの特徴です。しかし金利が高いため、開業資金を集める手段として得策とはいえません。
不動産業の開業資金の目安である400万円前後の融資であれば、日本政策金融公庫を活用すると良いでしょう。
▼不動産開業、どう成功させた?開業した方々の事例集公開中!
事例集資料をメールで受け取る
不動産開業で利用可能な日本政策金融公庫の2つの融資制度
不動産開業においては新規開業資金制度と新創業融資制度が利用できます。
新規開業資金制度と新創業融資制度の違いとは
新創業融資制度は日本政策金融公庫の他の融資制度と組み合わせてはじめて利用できます。新創業融資制度に単独で申し込むことはできないので注意が必要です。新創業融資制度を利用すれば、新規開業資金などの融資制度を無担保・無保証人で利用できるようになる点が特徴です。
新創業融資制度と組み合わせられる日本政策金融公庫の融資制度には、次のようなものが挙げられます。
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家支援資金
・新事業活動促進資金
参照:新創業融資制度
新規開業資金制度
新規開業資金制度は、新たに事業を始める方に対して、事業用設備や運転資金などに必要な資金を融資する制度です。不動産開業においては、事務所の家賃や仲介手数料などの経費に充てることができます。この制度の特徴は以下の通りです。
| 利用できる人 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内 |
|---|---|
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金 7年以内 |
詳しくは近くの支店へ問い合わせることが必要ですが、条件が非常に緩やかで、新規開業時に利用しやすい点が特徴です。
参照:新規開業資金
新創業融資制度
無担保・無保証人でも利用できる制度です。新たに事業を始める方、または事業開始後に税務申告を2期終えていない方を対象としており、他の融資制度との併用によるご利用となります。
| 利用できる人 | 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方。事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できる方* |
|---|---|
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 返済期間 | 設備資金 20年以内 運転資金 7年以内 |
*ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものになります。
不動産業の開業を目指す上で、資金以外にも準備すべきものはたくさんあります。
「開業に必要な法的手続き」「最新の法令への対応」「売り上げを大きく伸ばすためのインターネットを活用したHP制作・ポータルサイトへの出稿方法」「業務効率化を進めるシステムの導入」など、あげればキリがありません。
今まで「全国1,000店舗以上の開業を支援した」実績をもとに制作した、いえらぶの開業マニュアルでは「不動産の開業に必要なノウハウ」が全て記載されています。
無料でダウンロードできるため、不動産業の開業を検討している方は是非ご活用下さい。
▼不動産開業、どう成功させた?開業した方々の事例集公開中!
事例集資料をメールで受け取る
不動産開業の融資を受けるための3つの条件
不動産業を開業する際の融資を受けるためには、これから紹介する3つの条件を満たしましょう。また、なぜ必要であるのか、その理由についても解説します。
条件1.宅建業免許があるか?
1つ目の条件は、「宅地建物取引士(宅建士)」の資格取得です。この宅建士の資格は、不動産業を営むにあたって必須の資格になります。
融資を行う側からすると、取得前に融資を決定しても免許が取得できなければ返済が滞るおそれがあるためです。ただし、不動産の賃貸業のみを行う場合や、賃貸管理のみを営む場合には、この限りではありません。
不動産売買にかかわる仲介を行う場合には必須になるため、宅建士の資格は取得しておく必要があります。
条件2.自己資金があるか?
日本政策金融公庫では、自己資金の最低条件は融資額の1/10とされています。しかし、実際の融資金額は、自己資金と同額または倍額程度であることが多いため、ある程度の自己資金を準備することが必要です。
しかし、単に現金だけがあれば良いというわけでもありません。自己資金があることを証明するためには、毎月記帳している通帳があると効果的です。
現金だけ用意されていても、金融機関はそれが本当に本人のお金かどうかはまでは判断ができません。自分が貯めた分だと判断してもらえるように、通帳の準備も忘れずに行いましょう。
条件3.税金の未納分はないか?
融資を受けるための、3つ目の条件が「税金の支払い状況」です。
融資審査の段階で税金の支払い状況がチェックされるため、滞納があると金融機関からの借入はできなくなります。
新型コロナウイルスの流行によって事業に影響を受けた場合などの例外はあるものの、起業時の融資審査では、税金の未納は融資対象外と判断されやすくなります。事前に税金の支払い漏れがないか確認しておき、融資申請を行う前の段階で支払いは完了させておきましょう。
▼不動産開業、どう成功させた?開業した方々の事例集公開中!
事例集資料をメールで受け取る
不動産開業資金の融資を受ける際の注意点
借り入れ条件によって金利が異なる
日本政策金融公庫の「新規開業資金制度」は、通常よりも有利な条件で利用できる場合があります。
「女性、若者、シニアの方」「廃業歴等があり創業に再チャレンジする方」「中小会計を運用する方」などは、通常よりも有利な条件で利用可能です。
また、
・東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方
・解除区域が所在した市町村内において創業する方
これらに該当する場合なども借り入れの金利は下がります。
創業計画書に無理がないか
日本政策金融公庫から融資を受けるためには、創業計画書を作成して提出する必要があります。創業計画書とは、事業内容や目標、必要な資金や調達方法、事業の見通しや収支予測などをまとめた文書です。
「創業計画書」のテンプレート(日本政策金融公庫の公式サイト)はこちらです。記入例には大まかな内容しか書いていないので、ご自身の状況に合わせて、詳細な計画書を作成する必要があります。
下記が操業計画書の各項目になります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ①創業の動機 | 創業の目的や動機を記載 |
| ②経営者の略歴等 | 勤務先や業務内容、役職や経験を記載 |
| ③取扱商品・サービス | 商品やターゲット、競合や市場を記載 |
| ④取引先・取引関係等 | 販売先や仕入先、外注先を記載 |
| ⑤従業員 | 雇用予定の従業員人数を記載 |
| ⑥お借入の状況 | 既存の借入状況を記載 |
| ⑦必要な資金と調達方法 | 資金の調達方法と利用用途を記載 |
| ⑧事業の見通し(月平均) | 売上高や経費、利益を記載 |
創業計画書に無理があると判断されると、融資審査に通らない可能性が高くなります。創業計画書に無理がないかどうかチェックしておきましょう。
自分で作った創業計画書は、一度不動産開業のプロにチェックしてもらうのがおすすめです。
不動産開業のプロに相談することで、事業内容や市場分析、事業計画や財務計画などの項目について、現実的で有効なアドバイスを得られます。
また、現状利用できる融資・補助金についての案内や、売り上げを伸ばす方法・集客に関するアドバイスも受けられます。下記リンクから無料相談可能です。是非ご活用ください。
▼不動産のプロに開業について相談したい、という方へ
無料相談を予約する
開業資金の融資を受けるまでの流れ
日本政策金融公庫や銀行などから融資を受けるには、申請や面談などを通じて審査を通過する必要があります。
融資を見込んで起業する場合、融資が受けられないと開業自体が危ぶまれます。無事融資を通過するためにも、融資を受けるまでに必要なものや条件などを確認したうえで申請しましょう。
融資を受けるための手続きは「自分自身で行う」ケースと「認定支援機関を通じて行う」ケースの2パターンがあります。認定支援機関を通じて申請する場合には、まず最寄りの認定支援機関に相談すると良いでしょう。
具体的には、以下のような流れで融資申請から実行までの手続きを行います。
下記は、日本政策金融公庫の融資までの手順です。
| 1 | 「事業資金相談ダイヤル」へ電話するか、ホームページから融資相談をする |
|---|---|
| 2 | 必要書類の準備 |
| 3 | 日本政策金融公庫の支店窓口を訪問し、書類を提出 |
| 4 | 担当者との面談 |
| 5 | 担当者による現地調査・審査し、融資の可否判断を行う |
| 6 | 融資可能と判断されると、実際に資金が振り込まれる |
※必要書類(創業計画書、申込書、半年分の通帳コピー、過去2年分の源泉徴収書もしくは確定申告書、不動産の賃貸借契約書(店舗、自宅)、運転免許証のコピー、印鑑、印鑑証明書、水道光熱費の支払いが確認できる書類(3ヶ月分)など)
手順2で必要になる創業計画書は、ホームページからダウンロードすることができ、記入例なども例示されているので参考にして作成しましょう。
必要書類の中で、店舗分の不動産が未契約の場合には、契約を予定している不動産の見積書などでも問題ありません。また、融資を受けるまでには、申請からおよそ1ヶ月程度必要になります。開業までのスケジュールを逆算したうえで、余裕をもって申請を行いましょう。
融資を受けるための創業計画書の3つのポイント
金融機関から融資を受ける際、しっかりした創業計画書が必要です。創業計画書に書くべき内容をポイントで紹介します。
経営者の略歴等
これまでの略歴・実績等あれば必ず記載するようにしましょう。また、不動産業に関連する特許やノウハウなどを持っていればそれらも記載してください。
もし不動産業に関連する資格を持っていなければ、少しでも不動産業務に重なる・役立つ資格を書くようにします。たとえば、不動産業自体は経験がなくても、ファイナンシャル・プランナーなどの資格を持っていれば、その知識は記載すると良いでしょう。
ただし、略歴については嘘のないようにしてください。融資担当者は帝国データバンクや東京商工リサーチなどを通じて信用情報を調査しています。嘘の情報がバレてしまうと、融資を受けられなくなってしまう可能性が高いです。
必要な資金と調達方法
資金計画について記載するため、創業計画書の中でも最重要といえるものです。
特に、「自己資金の有無と金額」「調達資金全体における割合」は融資の判断に大きな影響を及ぼします。一般的に自己資金が多いほど経営が安定し、自己資金が少なく借入金が多いと債務不履行のリスクがあると判断されます。
また、自己資金の金額は、創業に対する本気度を言葉以外で示す大きなポイントになります。自己資金は通帳などで客観的に証明しないといけません。
他人からお金を借りて通帳残高を増やす「見せ金」行為が発覚した際は融資が行われない可能性が高いです。絶対にやめるようにしましょう。
事業の見通し
事業の収支がどのように推移して、どの程度の利益が確保されそうなのかを示すための項目です。借入金の返済ができるかの判断に関わるため、しっかりとした記述が必要だと言えるでしょう。
記載する金額は、すべて根拠を示しましょう。たとえば、不動産会社の月間売上高なら、「単価×物件数×成約率×月間営業日」で計算し、それぞれの数字は同業他社の平均値などを用いることが必要です。
この場合、単価は物件の平均価格、物件数は仲介可能な物件の数、成約率は物件を売買する確率、月間営業日は営業する日数を表します。これらの数字は、不動産市場の動向や競合状況によって変化するため、同業他社の平均値などを参考にすることが重要です。
個人的な経験や推測に基づいた数値は楽観的になりやすく、融資担当者に対して良い印象を与えないため注意が必要です。
▼不動産のプロに開業について相談したい、という方へ
無料相談を予約する
融資を受け取ったあとは業務の準備を始めよう
日本政策金融公庫やほか金融機関からの融資を受けとったら、開業に向けた準備に着手しましょう。不動産仲介業を行うのであれば、業務効率化に役立つ「いえらぶCLOUD」の導入がおすすめです。
いえらぶCLOUDは、不動産仲介に最適な業務効率化システムで、ホームページ作成やポータルサイトの連動、顧客管理、スケジュール管理まであらゆる業務を一気通貫で行うことができます。「開業時から業務効率化を定着させたい」「高い成約率を出すためにデータ分析を強化したい」など、不動産仲介業の効率化にはぜひ「いえらぶCLOUD」の導入をご検討ください。
まとめ
不動産業の開業にあたって、融資を受ける場合には事前に自己資金や資格取得などの準備が必要になります。
自分自身で融資申請の手続きを行うことも可能ですが、開業にあたってなにか不安があるなら、認定支援機関の活用も視野に入れておくと良いでしょう。
開業を成功させるためのお役立ち資料は下記からダウンロードできます。ぜひご活用ください。
【無料お役立ち資料】
不動産開業・独立成功の道