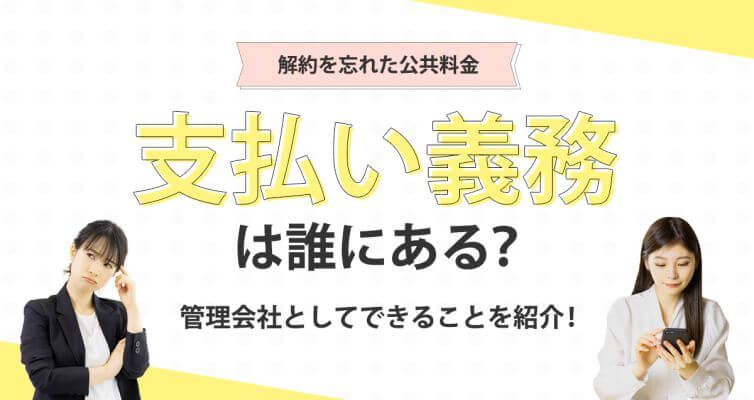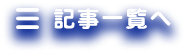抵当権付きの賃貸物件は大丈夫?抵当権が実行された場合などについて解説
タグ:
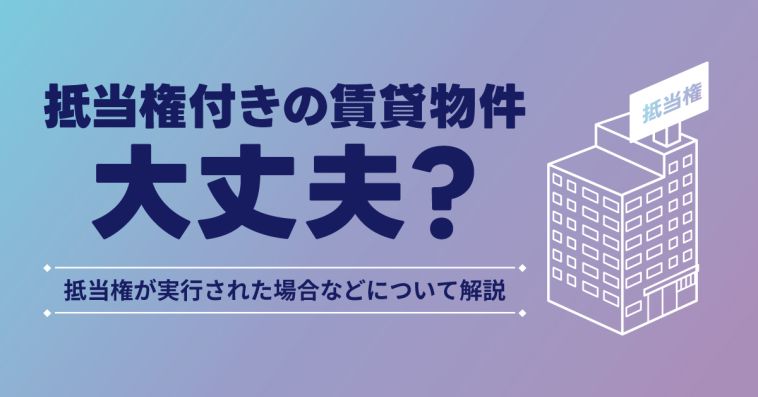
目次
▼賃貸管理業務がまるわかり
「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする
賃貸物件のオーナーチェンジは、各種の権利と義務が法的に新オーナーに継承されるため、賃借人には、賃貸人変更通知書を発行する程度です。
しかし、抵当権が実行された場合のオーナーチェンジは話が異なってきます。賃借人の方は「もし住んでいる物件の抵当権が実行されたらどうなるだろう?」と不安に思うでしょう。
そこで今回は、抵当権付きの賃貸物件で賃借人は大丈夫なのか、抵当権が実行された場合などについて解説します。安定した賃貸管理を行いたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
賃貸物件の抵当権とは?
まず、賃貸物件に付されている抵当権とは、どのようなものなのでしょうか?
抵当と抵当権
抵当とは、物件オーナーが金融機関からお金を借りる際に設定される担保のことです。賃貸物件の購入や建設をするために、あるいはほかの事業を目的に借りたローンの担保として、抵当権が設定されます。
物件オーナーのローンの返済が滞った場合に、担保としてその賃貸物件を競売にかけて、債権を回収する権利が抵当権です。
抵当権は、所有権などと同じように登記簿謄本に記載され、法的に認められた権利となります。
借りていたローンを完済したら、抵当権抹消の手続きをおこなうのは自己の居住用の物件と同じです。返済が終わっていない築浅の賃貸物件に、抵当権が付いているのはごく普通のことだと言って良いでしょう。
新オーナーは、立退きの正当事由が不要
もし抵当権が実行されたら?という話はこの次に詳述しますが、その場合のオーナーチェンジでは、立退きの話が出ないわけではありません。
通常、物件オーナーが入居者に立ち退きを依頼する際は、以下の2つが必要です。
①家賃の滞納や、物件の利用状況に問題があるなど信頼関係が損なわれたこと
②オーナーの事情での立退きの場合は「正当事由」をそなえること
正当事由とは、物件の使用を必要とする事情、賃貸借のこれまでの経過、物件の利用状況、立退料の給付などをさします。
抵当権の実行によってオーナーが変わると、新オーナーはこれらの正当事由をそなえることなく、賃借人に立退きを依頼することが可能なのです。
入居時には必ず抵当権の説明を
このような事実がある以上、賃貸借契約の際に、不動産管理会社は入居する方に「物件に抵当権が付いていて、立退きをお願いされる可能性がある」旨の説明が必要です。
ただ、以下のような点も併せてお伝えする必要があります。
そもそも抵当権の実行は、金融機関にとって債権の回収率も悪く、違う手段で返済を継続する話し合いなどをおこなうため、簡単には起こりません。
また、新しく物件を取得したオーナーも、寮などに使うなどの一部の例外を除き、ほとんどの場合は賃貸借を目的として購入するので、その場合退去の必要はありません。
入居する方の不安を取り除くのも、大事なポイントです。
▼賃貸管理業務がまるわかり
「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする
賃貸物件で抵当権が実行されるとどうなる?
つづいて、抵当権が実行された場合、どのようになるのかをおさらいしましょう。
物件オーナーの返済が滞る
ローンの滞納から6ヶ月ほどで、分割払いのできる「期限の利益」が失われ、物件オーナーはひと月以内に残債の一括返済を迫られます。
そこで返済ができなかった場合、保証会社による代位弁済がおこなわれ、債権者は金融機関から保証会社に移ります。
最初の滞納から8か月から9か月を経過した時点で、保証会社は裁判所へ不動産競売の申し立てをおこないます。
数週間後、競売開始が決定された旨が「競売開始決定通知」として、オーナーの自宅に届きます。
競売の流れ
競売開始決定通知から約2か月後までに、裁判所の執行官による物件調査を経て、オーナーに入札期間、開札日、売却基準価額などが記載された期間入札通知が届きます。
競売の情報は不動産競売物件情報サイト(BIT)に掲載され、誰でも見ることができますし、さらに詳細の情報を知りたい場合は、管轄の裁判所で書類を閲覧もできます。
1週間程度の入札期間を経て、入札期間の数日後に開札日となります。ここで物件を落札した方が、賃貸物件の新しいオーナーとなります。
新しいオーナーの意向に沿って退去の交渉
新しいオーナーが、現在の入居者に立ち退きを依頼する場合、退去までに6か月の猶予期間があります。
前述のように、新しいオーナーには立退きの際の正当事由は不要なので、すぐに退去の依頼が可能です。ここで賃借人が立ち退きたくない場合でも、オーナーは強制執行を実行することができます。
ただし、強制執行には相応の費用が必要なため、新オーナーは本来は必要のない立退料を支払うことで、和解の形をとることも多いです。
また、2004年から「抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」がスタートしています。これは抵当権者(この場合オーナーに対する債権者)全員の同意のもと、賃借人の賃借権と抵当権者の同意を登記しておくものです。
これによって、新オーナーに立ち退きしてほしい意向があっても、賃借人はその必要がなくなります。
▼賃貸管理業務がまるわかり
「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする
抵当権設定と、賃貸物件引き渡しの前後関係
また、抵当権設定と、賃貸物件の引き渡しの前後関係によって、賃借人の退去の義務には違いが出てきます。
抵当権設定が賃貸物件の引き渡しより後の場合
いままでご説明したのはすべてこのパターンで、抵当権設定のあとに賃借人が引き渡しを受けて入居した場合です。
この場合は、可能性は少ないものの、賃借人は抵当権の実行が原因で立退きをしなくてはならない可能性が生じます。
これは、賃借人は立退きのリスクを承諾したうえで契約したということになるため、賃借権では新オーナーの意向に対抗できなくなるからです。
抵当権設定が賃貸物件の引き渡しより前の場合
逆に、賃貸物件を引き渡したあとに抵当権が設定され、実行されてしまった場合はどうでしょう?
この場合は賃借権の方が優先となるため、賃借人は退去を求められても、応じる必要がありません。
したがって新オーナーが立ち退きを希望する場合は、一般的な賃貸借の状態と同じように正当事由をそなえたうえで賃借人と交渉したり、裁判に頼ることとなります。
▼賃貸管理業務がまるわかり
「賃貸管理業務マニュアル」をダウンロードする
賃貸の重要事項説明で抵当権を伝えないとどうなる?
このように管理会社がおこなう、抵当権の設定に関する重要事項説明は重い意味を持つのですが、仮におこなわなかった場合、どうなるのでしょう?
営業停止や免許取り消しの処分も
重要事項説明は、賃借人が取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得たうえで、賃借をするかを判断できるための説明です。
この重要事項説明を怠ったり、虚偽があった場合は、指示処分、業務停止処分、さらには宅地建物取引業者の免許取り消しの可能性があります。
指示処分に従わなかった場合の業務停止日数は、7日から30日とされ、さらに悪質であると認められた場合、免許取り消しとなります。
確実な入居を促す意図で、抵当権設定の事実を隠したりした場合、宅建業法による罰則のほかに、別途賃借人の居住権を侵害した形になった責任も問われることとなります。
まとめ
本記事では、抵当権付きの賃貸物件で賃借人は大丈夫なのか、抵当権が実行された場合などについて解説しました。
抵当権が設定されている物件では、重要事項説明で入居者に、抵当権とはどういうものか、実行されたときの退去の可能性について、しっかり説明をするようにしてください。
不安をあおるのではなく、退去の可能性がなくはないこと、最悪そのようになっても6か月の猶予がある点も、しっかり伝えると良いかと思います。正確かつ丁寧に説明できるように、抵当権について整理しておきましょう!
【無料お役立ち資料】
賃貸管理業務マニュアル